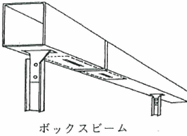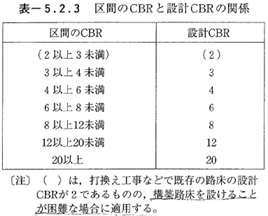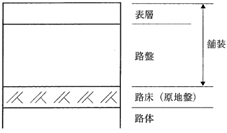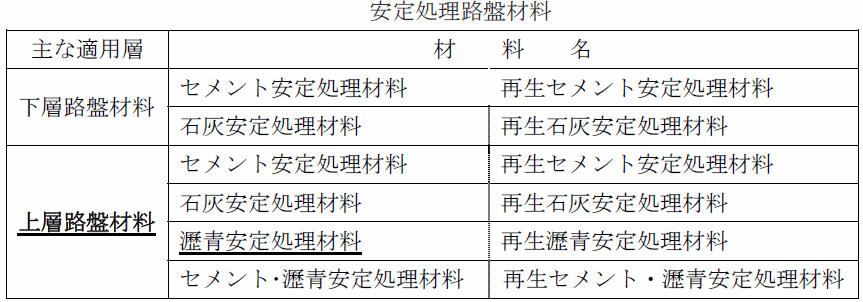|
|
|
�ߋ���� �O�̃y�[�W�� ���̃y�[�W��
|
| �y�� |
�P�z�@���̓��n�Ց�H�@�̂����A�t�̔�����}������H�@�������Ȃ������͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�v�����[�h�H�@ |
| (2) |
�o�C�u���t���[�e�[�V�����H�@ |
| (3) |
��t�����H�@ |
| (4) |
�T���h�R���p�N�V�����p�C���H�@ |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z�@ �v�����[�h�H�@�G���y�ډd�H�@�̈�H�@�ŁA�\�����̌��ݑO�ɓ��n�Ղɉd�����炩���ߍ��ى������Ă������Ƃɂ��A �S�y�w�̈�����i�s�����A �c�������ʂ̒ጸ��n�Ղ̋��x������}��H�@�ł���B�J���o�[�g���̍\�����̌v��ӏ��ɑ��ēK�p�����B�]���āA �t�}���H�@�ł͂Ȃ��B
�Q�ƁF(���H�y�H���n�Ց�H�w�j)
|
|
| �y�� |
�Q�z�@�R���N���[�g�̑ō���̗{���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�R���N���[�g�́A�{�����Ԓ��ɗ\�z�����U���A�Ռ��A�d�A�C���Ȃǂ̗L�Q�ȍ�p��
��ی삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
| (2) |
�R���N���[�g�́A�ō���A�d�����n�߂�܂ŁA�����̒��ˁA���Ȃǂɂ�鐅���̈�U
��h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
| (3) |
�R���N���[�g�̘I�o�ʂ́A�\�ʂ��r�炳�Ȃ��ō�Ƃ��ł�����x�ɍd������O�ɁA����
�{�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
| (4) |
�R���N���[�g�́A�\���ɍd�����i�ނ܂ŁA�d���ɕK�v�ȉ��x�����ɕۂ��A�ቷ�A�����A
�}���ȉ��x�ω��Ȃǂɂ��L�Q�ȉe�����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�R�j
�y����z
�@ �{�H�W���G8.2 �����{�� (2) �R���N���[�g�̘I�o�ʂ́A�\�ʂ��r�炳�Ȃ��ō�Ƃ��ł�����x���d��������������{�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�ƁF(�R���N���[�g�W��������(�{�H��))
|
|
| �y�� |
�R�z�@�h���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�K�[�h�P�[�u���́A�ԗ��Փˎ��̏Ռ��ɑ��ăP�[�u���̈�����Ǝx���̕ό`�Œ�R��
��h���ł���A���K�W�]���ɗD���B
|
| (2) |
�K�[�h���[���́A�j���ӏ��̋Ǖ���ւ����e�Ղł���B |
| (3) |
�{�b�N�X�r�[���́A��ɘH���p�Ƃ��Ďg�p�����B |
| (4) |
�K�[�h�p�C�v�́A�K�[�h���[���ɔ���K�W�]���ɂ����ėD��Ă��邪�A�{�H���ɗ��B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�R�j
�y����z�@ 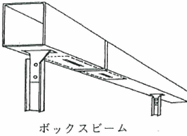
�{�b�N�X�r�[���͕\�����Ȃ����߁A�����їp�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ��L���ł���B
�Q�ƁF(�h���̐ݒu��E�����)
|
|
| �y�� |
�S�z�@�y�H�p���@�B�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�U���R���p�N�^�́A���̏�ɒ��ڋN�U�@�����t�������̂ŁA�U���𗘗p���Ē��ł߂��s���y�ʂȋ@�B�ł���B |
| (2) |
�^���p�́A�@�ւ̉�]�^�����N�����N�@�\�ŏ㉺���ɕς��āA�X�v�����O����đŌ�
�ɓ`�B������̂ŁA�Ō��ƐU����2�̋@�\������Ă���B
|
| (3) |
�U�����[���́A���[���ɋN�U�@��g�ݍ��킹�A�U���ɂ���ď����ȏd�ʂő傫�Ȓ��ł�
���ʂ悤�Ƃ�����̂ł���B
|
| (4) |
���[�h���[���́A��C����^�C���̓����𗘗p���Ē��ł߂��s�����̂ŁA�^�C���̐ڒn
���͍ډd����ы�C���ɂ��ω������邱�Ƃ��ł���B
|
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�S�j
�y����z 5-4-4���łߍ�Ƌy�ђ��łߋ@�B
�@ (1) ���[�h���[���G
�@�\�ʂ����炩�ȓS�ւɂ���Ē��ł߂��s�������ŁA�}�J�_���`�ƃ^���f���`�Ƃ�����B�]���Đݖ�(4)�^�C�����[���̐����ł���B
�Q�ƁF(���H�y�H���y�H�w�j)
|
|
| �y�� |
�T�z�@�y�؍H�����ʎd�l���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A����Ă�������͂ǂꂩ�B
|
| (1) |
�}�ʂƂ́A���D�ɍۂ��Ĕ����҂��������v�}�A�����҂���ύX�܂��͒lj����ꂽ�v
�}�A�H�������}�Ȃǂ������B
|
| (2) |
���L�d�l���Ƃ́A���ʎd�l����⑫���A�H���̎{�H�Ɋւ��閾�ׂ܂��͍H���ɌŗL�̋Z
�p�I�v�����߂�}���������B
|
| (3) |
����������Ƃ́A�����t���ɓ��D�Q���҂���o�����_������ȂǂɊւ��鎿��ɑ��Ĕ����҂����鏑�ނ������B |
| (4) |
�H�����ő����\�Ƃ́A�H���{�H�Ɋւ���H��A�v���ʂ���ыK�i�����������ނ���
���B
|
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�R�j
�y����z 1-1-1-2 �p��̒�`
10�D����������G����������Ƃ́A�H���̓��D�ɎQ��������̂ɑ��Ĕ����҂����Y�H���̌_���������������邽�߂̏��ނ������B
11�D������G ������Ƃ́A�����t���ɓ��D�Q���҂���o�����_��������Ɋւ��鎿��ɑ�
���Ĕ����҂����鏑�ʂ������B
�ȏォ��A�ݖ�(3)�͎�����̓��e�ł���B
�Q�ƁF(�y�؍H�����ʎd�l�����ʕґ�P�͑���)
|
|
| �y�� |
�U�z�@���H�̘H�����ʂ̈�ʓI�ȍ�Ə����̂����A�K���Ȃ����́A���̂ǂꂩ�B
�@���f���ʁ@�A���S�����ʁ@�B�ڍב��ʁ@�C��BM�ݒu���ʁ@�D�c�f����
|
| (1) |
�C �� �D �� �A �� �B �� �@ |
| (2) |
�C �� �A �� �@ �� �D �� �B |
| (3) |
�A �� �C �� �D �� �B �� �@ |
| (4) |
�A �� �C �� �D �� �@ �� �B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�S�j
�y����z ��4�� ���p���� ��2�� �H������
(�H�����ʂ̍ו�)��388���@�H�����ʂ́A���Ɍf���鑪�ʓ��ɍו�������̂Ƃ���B
�� ��ƌv��@�@�� ���`����@
�O ���S�����ʁ@�l ���a�l�ݒu���ʁ@�� �c�f���ʁ@�Z ���f���ʁ@�� �ڍב��ʁ@�� �p�n���Y�ݒu����
�Q�ƁF(��ƋK���̏��� ��4�� ���p����)
|
|
| �y�� |
�V�z�@�H���̎x���͕]���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
��Ԃ�CBR��10.5�̏ꍇ�A���Y�ӏ��̐vCBR��10�ł���B |
| (2) |
�u���ޗ��̏C��CBR��23.6�̏ꍇ�A�u���������w��CBR��20�ł���B |
| (3) |
�H�����[��1 m�̋ψ�Ȏ��R�n�Ղł���A����CBR��27�̏ꍇ�A�H����CBR��27
�ł���B
|
| (4) |
CBRm�̕��ϒl��4.9�ŕW������1.2�̏ꍇ�A��Ԃ�CBR��3.7�ł���B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z��Ԃ� CBR�Ɛv CBR4�̊W�͕֗��̕\-5.2.3�̒ʂ�ł���B
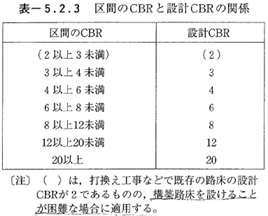
�]���āA�ݖ�(1)�� �vCBR��8�ł���B
�Q�ƁF(�ܑ��v�֗�)
|
|
| �y�� |
�W�z�@�ܑ��̐v�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�ԓ��ɂ�����ܑ��ɂ́A�K���\�w�Ɗ�w��݂���K�v������B |
| (2) |
��w�ɂ́A�ʏ�A�A�X�t�@���g���������p�����邪�A�R���N���[�g�ŁA����ޗ��Ȃ�
���p���邱�Ƃ��ł���B
|
| (3) |
�H�Ղ́A�ʏ�A��w�H�ՂƉ��w�H�Ղ�2�w���邪�A�����ɂ���Ă͘H�Ղ�l �w�ɂ��邱�Ƃ��ł���B |
| (4) |
�\���v�ɂ�����ܑ����́A�\�w�A��w�A�H�Ղ���јH���̍��v�����ł���B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�R�j
�y����z 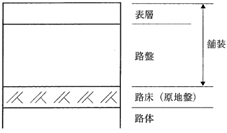
2-2-2 �e�w�̖����@(2)��w �B �ܑ����������ꍇ�́A ��w��݂��Ȃ����Ƃ�����B(�ݖ�1)
�@ ��w�ɂ��A�v���Ԃɂ킽���ĕ\�w���x����\���Ȉ��萫�A�H�Ղ̂���݂ɒǏ]�ł��� �\���Ȃ���ݐ��Ȃǂ����߂���B�]���āA����ޗ��͊Y�����Ȃ��B(�ݖ�2)
2-2-1 �ܑ��̍\���G�ܑ��͈�ʂɌ��n�Ղ̏�ɒz������邪�C���n�Ղ̂����C�ܑ��̎x���w�Ƃ��č\���v�Z���舵���w��H���Ƃ����C���̉�����H�̂Ƃ����B�܂��C���n�Ղ����ǂ���ꍇ�ɂ́C���̉��ǂ����w���\�z�H���C���̉�����H���i���n�Ձj�Ƃ����C���킹�ĘH���Ƃ����B�]���āA �ܑ��͘H��(���n��)�����������B(�ݖ�4)
5-2-1 ���ʓ��H�̍\���v�G(3)�\���v�@��ʗʋ敪N1����сAN2�̐v�ɂ����āC��w�H�ՂƉ��w�H�Ղ̍��v����15cm�����ɂȂ�ꍇ�́C���̂悤�ɐv����B
�vCBR��6�ȏ�̏ꍇ�C��w����щ��w�̋�ʂ������� �H�Ղ�̍ޗ��Őv���C�i���K�i�ɍ��킹�����l���Z�W�������̂܂ܗp����B(�ݖ�3) �@
�܂��C�vCBR��6�����̏ꍇ�́C��w����щ��w�H�Ղ���ʂ���2�w����Ȃ�v�Ƃ���B
�Q�ƁF(�ܑ��v�֗�)
|
|
| �y�� |
�X�z�@�R���N���[�g�ܑ��̐v�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�R���N���[�g�łɗp����R���N���[�g�̔z���v�ł́A�ꎲ���k���x����Ƃ���̂���ʓI�ł���B |
| (2) |
���ʃR���N���[�g�ܑ��̉��ڒn���ɂ́A�d�`�B���u�i�_�E�G���o�[�j��݂���B |
| (3) |
�H���́A���ډ����̑��茋�ʂ��狁�܂�v�x���͌W���A�܂���CBR�����̌���
���狁�܂�vCBR�ɂ���ĕ]������B
|
| (4) |
�R���N���[�g�ܑ��ɕW���I�ɗp������R���N���[�g�łɂ́A���ʃR���N���[�g�ŁA�A���S�R���N���[�g�ł���ѓ]���R���N���[�g�ł�����B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z�@ 6-2-1 ���ʓ��H�̍\���v
3) �R���N���[�g�Ō��̐ݒ��@�R���N���[�g�Ō��́C��ʏ����Ƃ��Đݒ肵���ܑ��v���ʗʂɉ����C�R���N���[�g�ܑ��̎�ނƎg�p����ܑ��p�R���N���[�g�� �v��Ȃ����x�����Ƃɂ��Đݒ�����B
�Q�ƁF(�ܑ��v�֗�)
|
|
| �y�� |
10�z�@�A�X�t�@���g�ܑ��ɗp����ޗ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
���ނɂ́A�ӐA�ʍӁA�����A�S�|�X���O�A���Ȃǂ�����B |
| (2) |
�Đ����ނɂ́A�Z�����g�R���N���[�g�Đ����ށA�A�X�t�@���g�R���N���[�g�Đ����ނ�
�ǂ�����B
|
| (3) |
�t�B���[�ɂ́A�Ε��A���ΊD�A�X�N���[�j���O�X�Ȃǂ�����B |
| (4) |
���ɂ́A�V�R���A�l�H���Ȃǂ�����B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�R�j
�y����z 3-3-2 �A�X�t�@���g�\�w���w���p�f�ށ@ (4)�t�B���[�@�t�B���[�ɂ́A�ΊD��₻�̑��̊�ӂ��� �Ε��A���ΊD�A�Z�����g�A����_�X�g����уt���C�A�b�V������p����B�������A�|�[���X�A�X�t�@���g�������ɂ́A�����Ƃ��ĐΊD��ӂ����Ε����g�p����B
�Q�ƁF(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
11�z�@�ܑ��ɗp�����l�ޗ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�����p�A�X�t�@���g���܂́A��Ƀ^�b�N�R�[�g�ɗp������B |
| (2) |
�|���}�[�����A�X�t�@���gH�^�́A��Ƀ|�[���X�A�X�t�@���g�������ɗp������B |
| (3) |
�Ζ��A�X�t�@���g���܂ɂ́A�Z���p�A�����p����уZ�����g�����p�Ȃǂ�����B |
| (4) |
�|���}�[�����A�X�t�@���g�ɂ́AI�^�A�U�^�A�V�^�����H�^�Ȃǂ�����B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z 3-3-2 �A�X�t�@���g�\�w���w���p�f��(1)�l�ޗ�4)�Ζ��A�X�t�@���g����
�@
�Ζ��A�X�t�@���g���܂́C�Ζ��A�X�t�@���g���E�ʊ����ܓ��Ő����ɕ��U���������̂ł���C��ʂ���ƐZ���p���܁C�����p���܂���уZ�����g�����p���ܓ�������B �Z���p���܂��C�V�[���R�[�g��A�[�}�[�R�[�g�Ȃǂ̕\�ʏ�����C�v���C���R�[�g���邢���^�b�N�R�[�g�Ɏg�p������B �����p���܂͏퉷�������Ɏg�p����C�Z�����g�����p���܂̓Z�����g�E�l���菈���H�@�Ɏg�p�����B
�Q�ƁF(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
12�z�@�A�X�t�@���g�ܑ��̘H�ՍނɊւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
����H�Սޗ��ɂ̓N���b�V�������◱�x�����ӐȂǂ�����B |
| (2) |
��ʂ��l���菈���ޗ��͉��w�H�Ղɗp������B |
| (3) |
��ʂɃN���b�V�������͉��w�H�ՂɁA���x�����Ӑ͏�w�H�Ղɗp������B |
| (4) |
�H�Ղɗp����ޗ��ɂ́A����ޗ��A���菈���ޗ��Ȃǂ�����B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�Q�j
�y����z 3-4-2�H�p�ޗ� (3)���菈���H�Սޗ�
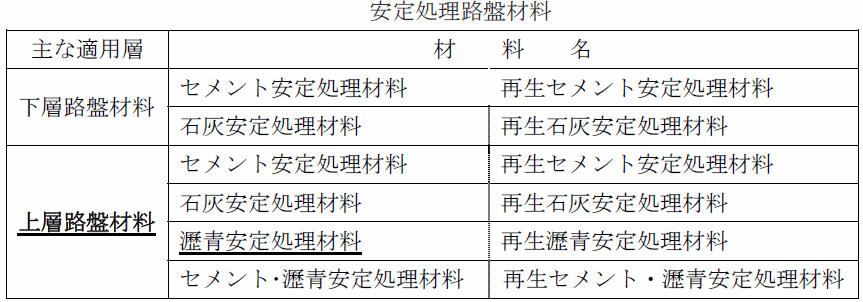
�Q�ƁF(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
13�z�@�ܑ��p�Z�����g�R���N���[�g�ɗp����ޗ�����єz���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�e���ނ���������ꍇ�A���`�A�ϋv���Ȃǂ��獻�����Ӑ��K���Ă���B |
| (2) |
�P�ʐ��ʂ́A�ܐݍ�Ƃ��ł���͈͓��łł��邾����������B |
|
| (3) |
�����ɕܐ݂���ꍇ�́A�x���`��AE�����܂̎g�p����������B |
| (4) |
���F�Z�����g�́A��r�I�����̌�ʊJ����K�v�Ƃ���ꍇ�Ɏg�p����B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�R�j
�y����z 3-3-3�R���N���[�g�p�f��
(1)�Z�����g�G�~�G�{�H���r�I�����̌�ʊJ����K�v�Ƃ���ꍇ�ɂ́C�����|���g�����h�Z�����g���g�p����̂���ʓI�ł���B�܂��C ���F�Z�����g���̍����Z�����g�́C�����ɂ킽�鋭�x�������ɗD��邪�C���̓����������邽�߂ɂ́C�\���Ȏ����{����K�v�Ƃ���ꍇ�������̂ŗ��ӂ���B(�ݖ�4)
(4)�e�����G�e���ނɂ́C�����i�썻���C�������C �C�����j �ӐΓ�������C ���x�C���`�C�ϋv���������썻�����K���Ă����B�������C�V�R���ނ̌͊����ɂ����肪����ɂȂ��Ă��Ă���B���̂��߁C��ʂɂ́CJISA 5005 �i�R���N���[�g�p�Ӑy�эӍ��j���邢�́C JISA 5011 �i�R���N���[�g�p�X���O���ށj�ɋK�肷��e���ނ��g�p���邱�Ƃ������B(�ݖ�P)
8-3-2 �R���N���[�g�̔z�������@�g�p����R���N���[�g�̔z���́C���v�̋��x�� �ܐݎ��̃��[�J�r���e�B�[��������͈͓��ŁC�P�ʐ��ʂ����Ȃ��C �o�ϓI�ȃR���N���[�g��������悤�ɁC�ȉ��̍��ڂɏ\���Ȕz�����s���Ȃ����߂�B(�ݖ�2)
�Q�ƁF(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
14�z�@�Đ��ܑ��p�ޗ��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�Z�����g�R���N���[�g�Đ����ނ��g�p�����Đ��H�Սޗ��́A�V�K���ނɔ�ׂďC��
CBR����r�I�������B
|
| (2) |
�A�X�t�@���g�������w�̐؍�ނ́A�A�X�t�@���g�R���N���[�g�Đ����ނ̕i���ɓK������Đ����M�A�X�t�@���g�������Ɏg�p�ł���B |
| (3) |
�Đ����M�A�X�t�@���g�������̔z���v�ɂ����āA���A�X�t�@���g�̐����������
���߁A�Đ��p�Y���܂ɂ��j���x��������@������B |
| (4) |
��ʌ��n�̃Z�����g�R���N���[�g�����ނɂ́A�^�C���ⓩ����ށA�p�{�[�h�ށA�ؕЂȂǂٕ̈����������Ă���ꍇ������B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z 2-4-2�Đ��H�Սޗ�
�A �Z�����g�R���N���[�g�Đ����ނ́C�V�K���ނƔ�ׂĖ��x���������C�z��������т��茸�茸�ʂ��傫���Ȃ�X���ɂ��邪 �C��CBR�͔�r�I�傫�����Ƃ���P�Ƃł��Đ��N���b�V�������Ƃ��ė��p�ł�����̂�����B
�Q�ƁF(�ܑ��Đ��֗�)
|
|
| �y�� |
15�z�@�H�Ղ̎{�H�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
����H�Ղ̎{�H�ɂ����āA�~�J�Ȃǂɂ��ޗ��������������܂ݒ��ł߂�����ȏꍇ��
�́A���V��҂��Ĕ��C�������s�����Ƃ�����B
|
| (2) |
�ΊD���菈���H�Սޗ��̒��ł߂́A�œK�����������⎼����Ԃōs���Ƃ悢�B |
| (3) |
�Z�����g���菈���H�@�ɂ����āA���łߏI���㒼���Ɍ�ʊJ�����Ă������x���Ȃ����A
�K�v�ɉ����ăA�X�t�@���g���܂��U�z����Ƃ悢�B
|
| (4) |
���M�A�X�t�@���g���菈���H�Սޗ��̕~���Ȃ炵�́A��ʂɃu���h�[�U���g�p���邪�A
�A�X�t�@���g�t�B�j�b�V����p���邱�Ƃ�����B
|
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�S�j
�y����z�@ 5-4-3 �l���菈���H�Ղ̎{�H (2)�{�H
�B �~�ς��ɂ́C��ʂɃA�X�t�@���g�t�B�j�b�V����p�������C�܂�Ƀu���h�[�U��[�^�[�O���[�_�Ȃǂ�p���邱�Ƃ�����B
�Q�ƁF(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
16�z�@���M�A�X�t�@���g�������̐����E�^���Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�ŏ��̃o�b�`�́A�K���Ȕz���ƂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ�����̂ŁA�g�p���Ȃ����Ƃ��]�܂�
�����B
|
| (2) |
�o�b�`���v�����g�ł͍ח����̑����������́A�������Ԃ�ʏ�����Z������B |
| (3) |
�o���̍������̖ڎ��ώ@�́A�v�����g�̐ݔ�������������Ă���̂ŏȗ����邱�Ƃ�
�ł���B
|
| (4) |
�A�X�t�@���g���������^���ԉב�ɕt������̂�h�~���邽�߂ɁA�y�����ב�ɓh�z����B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z�@
4-2-3 �V�K�������̐��� (2) �o�b�`���v�����g�̗��ӎ���
2) ��ʂɍ������Ԃ�30�`50�b�ł��邪�A �ח����̑����������Ȃǂ́C�������Ԃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B(�ݖ�2)
5-3-2 �^���Ԃ̐ύ��ݏ����Ə��ԁ@(1)�����@
�A�X�t�@���g�������̕t����h�~���邽�߂��d���A�������邢�͐Ό����Ȃ���h�z �����āA�ύ��݂܂őҋ@������B(�ݖ�4)
5-3-3 �^����Ƃ̒��ӎ����@(2)�A�X�t�@���g�������̊ώ@�Ɖ��x����@
�A�X�t�@���g�����������S���҂́A �^���Ԃɐςݍ��A�X�t�@���g�������̖ڎ��ώ@�Ɖ��x������s���B(�ݖ�3)
�Q�ƁF(�A�X�t�@���g�������֗�)
|
|
| �y�� |
17�z�@���M�A�X�t�@���g�ܑ��̒��ł߂Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
���[���ɂ��]���ł́A��ʂɋ쓮�ւ��A�X�t�@���g�t�B�j�b�V�����Ɍ����čs���B |
| (2) |
�U�����[���ɂ��]���ł́A�]�����x���x������ƕs���⏬�g���������₷���B |
| (3) |
���łߍ�Ƃ́A��ʂɏ��]���A�p�ړ]���A�]������юd�グ�]���̏����ōs���B |
| (4) |
���]���̓w�A�N���b�N�̐����Ȃ�����ł��邾���Ⴂ���x�ōs���B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z�@ 6-4-5���ł�
���łߍ�Ƃ́A�p�ړ]���A���]���A�]������юd�グ�]���̏����ōs���B(�ݖ�3)
(1)���]�� 2) ���]���̓w�A�N���b�N�̐����Ȃ�����ł��邾���������x�ōs���B(�ݖ�4)
(2)�]�� 3) �U�����[���ɂ��]���ł́C�]�����x������������s���⏬�g����������B�܂��C�x������Ɖߓ]���ɂȂ邱�Ƃ�����̂ŁC�]�����x�ɒ��ӂ���B(�ݖ�2)
�Q�ƁF (�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
18�z�@�|�[���X�A�X�t�@���g��������p�����r�����ܑ��̎{�H�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�^�C�����[���ɂ��d�グ�]���́A�������̕\�ʉ��x��70�����x�ɂȂ��Ă���s����
���]�܂����B
|
| (2) |
��ʂ̖����x�A�X�t�@���g�������ɔ�r���Ď��ԓ�����̐����ʂ������B |
| (3) |
�^�b�N�R�[�g�̎U�z�ʂ́A��ʂ�0.4�`0.6 L/�u���W���ł���B |
| (4) |
����t���ŏ������́A�e���ނ̍ő嗱�a�ȏ�Ƃ���B |
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�Q�j
�y����z�@ 7-3-1�����y�щ^��
�@ (2)�����@�|�[���X�A�X�t�@���g�������́A�A�X�t�@���g�������ɂ����ēK�ȉ��x�Ǘ��E�i���Ǘ��̂��ƂŐ�������B�Ȃ��C�A�X�t�@���g�v�����g�̐����\�͂��A �����x�A�X�t�@���g���������̐������Ɣ�r����60%���x�ɒቺ�����̂ŁA�H���v��ɑg�ݍ���ł������Ƃ��K�v�ł���B
�Q�ƁF(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
19�z�@���ʃR���N���[�g�ł̎{�H�Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�X�����v5cm�ȏ�̃R���N���[�g�̉^���̓_���v�g���b�N�ōs���̂���ʓI�ł���B |
| (2) |
�R���N���[�g�̕~���Ȃ炵�́A�X�v���b�_�ōs���̂���ʓI�ł���B |
| (3) |
�R���N���[�g�̉��낵�́A�o�b�N�z�E�Ȃǂ̃o�P�b�g���g�p���邱�Ƃ�����B |
| (4) |
�R���N���[�g�̗���������ܐ݊J�n�܂ł̎��Ԃ̌��x�̖ڈ��́A�A�W�e�[�^�g���b�N��
���^���̏ꍇ�Ŗ�1.5���Ԉȓ��Ƃ���B
|
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�P�j
�y����z 8-2-4�R���N���[�g�̐����Ɖ^��
(2) �^��
1) ��ʂɁC �X�����v 5cm �����̍d����R���N���[�g����ѓ]���R���N���[�g�̉^���̓_���v�g���b�N�ōs���X�����v 5cm �ȏ�̃R���N���[�g�̉^���̓A�W�e�[�^�g���b�N�ōs���B
2) �R���N���[�g�̗���������C�ܐ݊J�n�܂ł̎��Ԃ̌��x�̖ڈ���,�_���v�g���b�N�ɂ��^���̏ꍇ�Ŗ� 1 ���Ԉȓ��C �A�W�e�[�^�g���b�N�ɂ��^���̏ꍇ�Ŗ� 1.5 ���Ԉȓ��Ƃ���B
8-4-3 ���ʃR���N���[�g�̎{�H
(5) ����ꂨ��щ��낵�G���낵�ɂ��C�{�֗��́u4-4 �R���N���[�g�ܑ��̎{�H�@�B�v�Ɏ��������낵�@�B(�����^�@�A�c���^�@�A�v���[�T�X�v���b�_)�̑��ɁC �o�b�N�z�E���̃o�P�b�g���g�p���邱�Ƃ�����B
(6)�~���Ȃ炵�G�R���N���[�g�̕~���Ȃ炵�́C�~���Ȃ炵�@�B�i�X�v���b�_�j��p���čs���C�S�̂��ł��邾���ϓ��Ȗ��x�ɂȂ�悤�ɓK�ȗ]�������čs���B�~���Ȃ炵�́C�S�Ԃ�p����ꍇ��2�w�ŁC�S�Ԃ�p���Ȃ��ꍇ��1�w�ōs���B
�Q�ƁF�@(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
| �y�� |
20�z�@�e��ܑ̕��Ɋւ��鎟�̋L�q�̂����A�s�K���Ȃ����͂ǂꂩ�B |
| (1) |
�t�H�[���h�A�X�t�@���g�ܑ��Ƃ́A���M�A�X�t�@���g������������ۂɁA���M����
�A�X�t�@���g��A��ɂ��A�����������߂Đ���������������p����ܑ��ł���B
|
| (2) |
�r�����ܑ��Ƃ́A���̍����ޗ���\�w�܂��͕\�E��w�ɗp���A�J���Ȃǂ����݂₩�ɘH�Ոȉ��ɐZ��������ܑ��ł���B |
| (3) |
�Ӑ}�X�`�b�N�������ɑ@�ێ��⋭�ނ�p����ꍇ�A�������Ԃ�ʏ��蒷������Ȃ�
�̑K�v�ƂȂ�B
|
| (4) |
���ʕܑ��̕\�w�Ƀ|�[���X�A�X�t�@���g��������p����ꍇ�́A���Ɋ�w�̑ϔ�������
�z������K�v������B
|
|
�Ɖ��:
��---�@ �i�Q�j
�y����z�@ 9-3-1�r���@�\��L����ܑ�
(2) �r���@�\��L����ܑ��̎���G �r�����ܑ��Ƃ͋��̍����ޗ���\�w�܂��͕\�E��w�ɗp���J���������݂₩���H�ʉ��ɐZ�������r��������ܑ��ł���B���̏ꍇ�C���w�ɂ͎Ր����̑w��݂��邱�Ƃ��� �H�Ոȉ��ɐ��͐Z�����Ȃ��\���ƂȂ�B
�Q�ƁF(�ܑ��{�H�֗�)
|
|
|
|
|
|
|
|